EV化で多段変速やクラッチが不要になっても、運転の楽しさは失いたくありません。
そこで注目されるのが、BMW MとMINIが共同で進めるEV向けの“マニュアル体験”です。
擬似的なギアチェンジ、回生制御による減速感、車内音の演出を緻密に組み合わせ、シフト操作のリズムと手応えを電動化時代に再現しようとしています。
2026〜2027年に登場予定のNeue Klasse世代や、次期MINI JCWでも採用が噂され、上位モデルでは850馬力級でも“操る喜び”を失わない設計が目標です。
本記事では開発の背景、狙い、導入が見込まれる技術とモデルを整理し、EVでも本能的に楽しい運転体験の実現可能性をわかりやすく解説します。
- EVで操る楽しさ再現:擬似変速と音・振動制御で、EVでもシフトのリズムと没入感を実現。
- BMW MとMINIの戦略:グループ技術でM3 EVやMINI JCWに展開、体験価値で差別化。
- 他社事例で裏付け:Ioniq 5 Nやトヨタ試作が示す、体験重視の潮流と実装ポイント。
EV時代とマニュアル消滅の現実
EVはなぜ多段変速を必要としないのか
電気モーターは停止直後から最大トルクを発生し、広い回転域で効率良く力を引き出せます。
そのため、内燃機関のように狭い有効回転域を補う多段ギアは基本的に不要です。
加えて、逆起電力を活かす回生ブレーキにより、減速時のエンジンブレーキ相当の挙動も再現できます。
結果として、EVでは“速さ”と“効率”に限れば単速固定減速機で十分という結論になります。
実際、多くの量産EVは1段固定で0〜時速100kmを力強く加速し、高速域でも変速なしで巡航します。
それでも消えない“シフトの快感”
一方で、運転の満足度は加速性能だけで決まりません。
シフトのタイミングを読み、回転を合わせ、減速で姿勢を整える一連の所作は、ドライバーが速度と路面を直感的に把握するための大切な手がかりです。
視覚に頼らず耳と手足で“今どのくらい速いか”を察知できるからこそ、峠道やサーキットでリズムが生まれ、操っている実感が高まります。
現行の内燃Mモデルでは地域によって手動変速の支持が根強く、電動化後も“操る感覚”をどう残すかがブランド価値の要になります。
次期M3のEV版は三ペダルを採用しない見込みですが、その代わりに擬似変速や触覚・聴覚のフィードバックで、走りのリズムと情報量を補う方向へ発想が切り替わっています。
BMW MとMINIが挑む「人工トランスミッション」
脳とクルマをつなぐ新しいインターフェース
BMW Mのフランク・ファン・ミールCEOは
「純粋なEVは静かで速いが、ドライバーの脳と直結する感覚が失われてしまう」
と語っています。
従来の内燃モデルでは、ギアの選択やシフトダウンの瞬間に得られる音や振動が重要な情報でした。
しかしEVは一速固定で変速がなく、モーター音も小さいため、速度感覚をつかみにくいのが課題です。
BMWはこれを補うため、擬似的にシフトを体験できる“人工トランスミッション”の開発を数年前から進めています。
単なる演出ではなく、ドライバーの集中力やリズムを取り戻す技術として位置付けられているのが特徴です。
シミュレーテッドシフトの仕組み
人工トランスミッションはソフトウェアと車両制御を駆使し、変速感やエンジンブレーキのような挙動を再現します。
アクセルを踏み込むと仮想的なギア比に応じて加速感が変化し、シフト操作を行えばわずかなトルク抜けと加速のつながりを感じられるように設計されます。
さらに回生ブレーキを細かく制御し、シフトダウン時に“回転合わせ”が行われたかのような減速挙動を演出します。
これによりドライバーは「いま三速にいる」「次は二速へ落とす」といった意識を持ちながら走れるようになります。
速度計を注視しなくても感覚的に車速を把握でき、サーキット走行のように一瞬の判断が求められる場面で大きな効果を発揮します。
音と振動が生み出す没入感
BMWは音響にも力を入れています。
既存のEV向けには映画音楽家ハンス・ジマーと共同開発した「IconicSounds Electric」を提供していますが、Mモデルではより攻撃的でメカニカルな音を用意する方針です。
低速では重低音のうなり、高回転域では咆哮のようなサウンドを合成し、仮想ギアチェンジに合わせて音量やトーンを変化させる仕組みです。
さらにシートやステアリングに細かな振動を加えることで、エンジンが唸るようなフィードバックを再現。
五感に訴える情報を積み上げることで、EVでありながら従来のMモデルに近い没入感を狙っています。
Neue Klasse世代M3 EVでの導入見込み
2027年に登場予定のNeue KlasseベースM3 EV(開発コードZA0)は、最大850馬力級の出力を持ち、前後に異なるモーターを組み合わせた4モーター構成が想定されています。
リアには応答性の高い同期モーター、フロントには効率重視の非同期モーターを採用し、状況に応じて緻密に駆動力を配分します。
この制御に人工トランスミッションを組み合わせることで、圧倒的なパワーを単なる“直線の速さ”ではなく“操る楽しさ”へと昇華させる狙いがあります。
BMWは公式にマニュアルを採用しないと明言しましたが、その代替としてシミュレーテッドシフトを進化させる方針を示しています。
MINIへの展開と小型EVの可能性
BMWグループ内で同じくドライバー志向を重視するMINIも、この技術を共有する立場にあります。
特にハイパフォーマンスグレードのJCW(ジョンクーパーワークス)は、歴代モデルがコンパクトな車体と軽快な操作感で愛されてきました。
そのDNAをEV時代に引き継ぐには、単なる加速性能以上に「操作して楽しい」仕掛けが必要です。
MINI向けにはパドルでのシフト操作や簡易クラッチペダルを用いた実験も行われており、将来的に“電動マニュアルMINI”として特別仕様車が登場する可能性も語られています。
これが実現すれば、BMW Mがサーキットでの集中力を重視するのに対し、MINIは日常走行やワインディングで“操る喜び”をより身近に届ける存在となるでしょう。
技術以上に大切な「ブランド体験」
EV化の流れの中でマニュアルは効率的には不要ですが、BMW MとMINIにとってはブランド価値の中核を担う要素です。
人工トランスミッションは数値上の速さを競うものではなく、ドライバーが「クルマと一体になる感覚」をどう維持するかに焦点を当てています。
これによりBMWグループは“ただ速いEV”ではなく“走る喜びを味わえるEV”を提供することができ、他メーカーとの差別化につながります。
運転そのものを楽しみたい人に向けて、電動化時代における新しいスポーツカー像を提案しているのです。
他メーカーの挑戦が示すヒント
ヒュンダイ Ioniq 5 N の「e-shift」

BMWやMINIだけでなく、他メーカーもEVでマニュアル体験を再現する試みを進めています。
代表的な例がヒュンダイのIoniq 5 Nに搭載された「e-shift」です。
8速ATを模した制御で、シフトダウン時には回転数を合わせるような挙動を再現し、さらに回生ブレーキを組み合わせてエンジンブレーキの感覚を与えます。
これにより加速や減速にリズムが生まれ、ドライバーは速度変化を直感的に把握しやすくなっています。
単なる演出に留まらず、走行中の緊張感と没入感を高める技術として評価されています。
トヨタのクラッチ付きEV試作車

トヨタもまた、EVにマニュアル体験を持ち込む開発を進めています。
特徴的なのはクラッチペダルとシフトレバーを備え、実際にクラッチ操作を行わなければ発進できない仕組みです。
場合によってはエンストするように設計されており、初心者がマニュアル車を習得する過程まで忠実に再現しています。
実用性以上に「運転の奥深さ」を残すことを狙っており、BMWやMINIが進める人工トランスミッションと同じ方向性であることが分かります。
ジープ Wrangler Magneto の6速MT

さらにユニークな事例として、ジープがコンセプトカー「Wrangler Magneto」に実際の6速マニュアルを組み合わせた試みがあります。
これは電動モーターに物理的なギアボックスを組み込んだ希少な例で、EVでありながら従来型の変速操作を完全に体験できる仕様です。
市販化は想定されていませんが、ファンに強烈な印象を与え、「EVでもマニュアルが楽しめる」というメッセージを発信しました。
共通するキーワードは「体験重視」
これらの事例に共通するのは、効率や性能よりも「体験」を重視している点です。
EVは理論上シンプルで扱いやすい乗り物ですが、走りを楽しむためには余計とも思える複雑さが必要だと各メーカーが考えているのです。
BMWとMINIが開発する人工トランスミッションも、この流れの中で必然的に生まれた取り組みといえます。
他社の成果や反響は、BMWグループがEV時代でも「運転の楽しさ」を提供し続けるための大きなヒントとなっています。
EVマニュアルの価値と今後の展望
「不要論」と「体験重視論」のせめぎ合い
EVにマニュアルは不要という意見は技術的には正解です。
多段変速をなくせば軽量化と効率化が進み、製造コストも抑えられます。
しかし「シフトを操る楽しさ」を求める声は依然として大きく、BMWやMINIの挑戦はそのニーズに応えるものです。
単なる効率や性能比較では測れない価値をどう残すかが、今後のEVスポーツカーにとって重要な課題といえます。
ブランド価値を守るBMWとMINI
BMW Mは「究極のドライビングマシン」を掲げ、MINIは「ゴーカートフィーリング」をブランドアイデンティティとしてきました。
もしEV化でシフト体験を完全に失えば、両ブランドの魅力は大きく損なわれるでしょう。
そのため人工トランスミッションやシミュレーテッドシフトは、単なる遊びではなくブランドの存続戦略に直結しています。
今後数年で登場するNeue Klasse世代のM3や次期MINI JCWは、その象徴的なモデルとなるはずです。
EVでも「楽しいクルマ」を目指す方向性
EVマニュアル計画は効率を犠牲にしてでも「運転する喜び」を再現しようとする姿勢の表れです。
850馬力級のM3 EVが人工トランスミッションでサーキット走行の没入感を提供し、MINI JCWが日常の街乗りでも操る楽しさを届ける。
こうした両輪での展開は、BMWグループがEV時代においても「ただ速いだけのEV」ではなく「心を動かすクルマ」を提供し続けるという強いメッセージといえるでしょう。
まとめ:EVマニュアル計画が示す未来
EVにマニュアルは不要という常識を覆す挑戦が、BMW MとMINIによって進められています。
人工トランスミッションやシミュレーテッドシフトは、走行効率よりも「操る感覚」を優先した技術であり、ブランドの核心を守る試みです。
2026〜2027年に登場予定のNeue Klasse世代や次期MINI JCWは、その実現に向けた第一歩となるでしょう。
EV時代でも「運転は楽しい」と胸を張れる未来が近づいています。
Reference:motoringfile.com / motorillustrated.com
よくある質問(FAQ)
Q1. EVにマニュアルは本当に必要ですか?
A. 走行効率の観点では不要ですが、運転の楽しさや速度感の把握など「体験価値」を高める目的では意味があります。人工トランスミッションやシミュレーテッドシフトは、その体験をEVで再現するための手段です。
Q2. BMW M3のEV版に三ペダルのマニュアルは搭載されますか?
A. 2027年登場見込みのM3 EVは三ペダルの採用は想定されていません。その代替として、擬似的な変速感や音・振動などのフィードバックを組み合わせ、集中力とリズムを取り戻す設計が検討されています。
Q3. MINIにもEV向け“マニュアル体験”は導入されますか?
A. グループ内で技術を共有する前提で、MINIのJCWなどドライバーズモデルへの展開が期待されています。日常域での楽しさを重視し、パドル操作中心のシミュレートや限定仕様での発展が想定されます。
Q4. 具体的にどんな仕組みで変速感を再現するのですか?
A. ソフトウェア制御で仮想ギア比を設定し、シフト操作に合わせてトルクのつながりや回生ブレーキ量を調整。エンジンブレーキ風の減速や“回転合わせ”のような挙動を作り、音響と微振動も同期させます。
Q5. 本物の多段ギアをEVに載せる案は非現実的ですか?
A. 物理ギア搭載の試作例はありますが、重量・コスト・効率の面で量産には不利です。現在はソフトウェアと統合制御で体験を高めるアプローチが主流で、軽量・高効率と“楽しさ”を両立しやすいのが利点です。
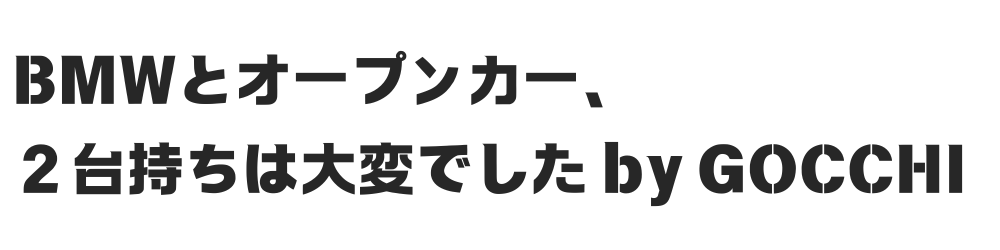


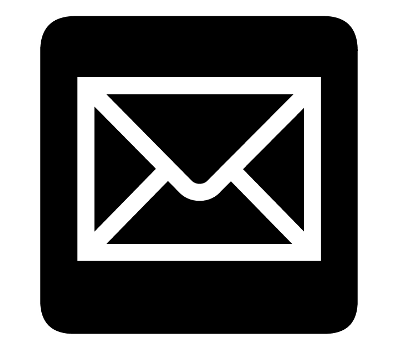


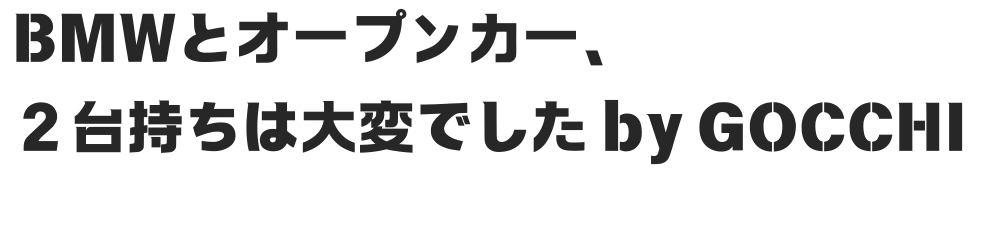
コメント