BMWファンの中には、「マニュアルこそが真のドライバーズカー」と信じる人も少なくありません。
しかし、時代の流れとともに、BMW Mモデルにおけるマニュアル車の存続が厳しくなっています。
なぜマニュアルが廃止されるのか?
それには、単なる「売れないから」ではなく、技術的な理由が深く関わっています。
本記事では、BMWが直面する「馬力の壁」とマニュアル車に課された限界、そしてごく一部にだけ許された“例外”の存在を掘り下げます。
- 馬力制限の理由を解説:マニュアル車が473馬力で止まる技術的背景を明確に。
- EV時代のM3に変化:2027年のM3 EVではマニュアルが非搭載に確定。
- 限定車3.0 CSLの特例:唯一の例外としてマニュアル搭載が許可された限定モデル。
馬力の限界:なぜ473馬力がマニュアルの上限なのか

M2 CSがマニュアル非搭載となった理由
2025年に発表されたBMW M2 CS(G87型)は、多くのファンの期待に反して、6速マニュアルトランスミッション(6MT)の設定がありませんでした。
その理由は明確で、BMW M部門の開発責任者ディルク・ヘッカー氏によれば、
「マニュアルトランスミッションは最大でも473馬力、550Nmのトルクまでしか対応できない」
という技術的な制限があるからです。
マニュアルの構造上の限界
BMWが現在採用している6MTは、構造上の耐久性に限界があります。
S58型直列6気筒ツインターボエンジンは、理論上500馬力以上を発揮可能ですが、マニュアル車ではトルクと出力を制限しなければ安全性や信頼性の基準を満たせません。
そのため、マニュアル仕様では473馬力/550Nmが限界とされており、より高出力のモデルには自動変速機が選ばれることになります。
性能優先の決断
M2 CSは、サーキットでの性能やラップタイムが求められるハイパフォーマンスモデルです。
BMWはこのモデルにおいて、最大出力523馬力/650Nmを実現するため、マニュアルではなく8速ステップトロニックATを採用しました。
つまり、運転の“楽しさ”ではなく、性能面を優先した判断だったといえます。
473馬力という“壁”
このように、BMWのマニュアル車が直面する“馬力の壁”とは、まさにこの473馬力という数値そのものです。
マニュアルでそれ以上の出力を実現するには、現行の構造やコスト、耐久性、安全性の壁を超える必要があります。
結果的に、BMWは高性能モデルにはマニュアルを搭載しない方針を強めています。
3.0 CSLだけが許された理由とは:特例的な存在

限定モデルにだけ許された高出力マニュアル
BMWのマニュアル車における“馬力の壁”を超えた唯一の例外が、2023年に発表された3.0 CSLです。
このモデルは、M4 CSLをベースにした50台限定の超高級スポーツカーで、最高出力は553馬力と、マニュアル車としては異例の高出力を誇ります。
それにもかかわらず、6速マニュアルが採用されており、多くのファンを驚かせました。
なぜマニュアルが搭載できたのか?
この特例が成立した背景には、いくつかの条件があります。
まず、3.0 CSLはごく少数生産であり、公道走行よりも“コレクターズアイテム”としての位置づけが強いモデルです。
そのため耐久性や長期使用に関する社内基準が、通常の量産車よりも緩やかに設定されていた可能性があります。
また、実際のトルクは550Nmに抑えられており、マニュアルの許容範囲内に調整されています。
価格と限定性が可能にした“例外措置”
3.0 CSLの販売価格はおよそ75万ユーロ(日本円で約1億2千万円)とされており、量産モデルとは異なる“特別な約束”のもとで開発された車です。
このような背景があったからこそ、BMWはマニュアル搭載に踏み切ることができたのです。
結果として、このモデルは「マニュアルで乗れる最後の真のM」とも称されました。
2027年、M3 EVにマニュアルは存在しない

BMW M CEOが公式に否定
BMW M部門のCEO、フランク・ファン・ミール氏は2025年、イタリアで開催された「コンコルソ・デレガンツァ・ヴィラ・デステ」において、次期M3 EVにはマニュアルトランスミッションを採用しないと明言しました。
これはBMWが本格的に電動化へ舵を切ることを意味し、パフォーマンスモデルにおける大きな転換点となります。
850馬力のパワーとEV構造の特性
2027年に登場予定のM3 EV(開発コード:ZA0)は、BMWの次世代EVプラットフォーム「Neue Klasse」をベースにし、最大出力850馬力以上が想定されています。
この膨大なパワーは、前後に独立したモーターを備える4モーター構成によって実現されるとされ、ガソリン車の駆動系とはまったく異なる制御が求められます。
こうした構造では、マニュアルギアボックスはそもそも不要で、効率性・応答性の面からも不利になるため、採用は見送られました。
マニュアルに代わる“ドライバーとの対話”

BMWはマニュアルトランスミッションの“運転する楽しさ”を代替するため、EV専用のフィードバック技術を開発中です。
たとえば、擬似的なエンジンサウンドを室内に流す「合成サウンド」や、アクセルペダルやステアリングから伝わる「触覚的な反応」、さらには加速感と連動した映像表現など、五感を通じてドライバーとの一体感を保つ工夫が試されています。
ただし、これらがマニュアルの直感的な操作性を完全に置き換えることは難しいと見られています。
マニュアルの終焉か?今後のICE Mモデルの行方

M2だけが最後の砦?
BMWはマニュアルトランスミッションを搭載する内燃エンジン(ICE)モデルとして、当面はM2を残す方針です。
実際、アメリカ市場では新車購入者の半数以上がM2のマニュアルを選んでいるとされ、一定の需要があることがわかります。
そのためM2に関しては、2029年頃まではマニュアル仕様が生産される可能性が高いと見られています。
M3/M4、Z4など他モデルは廃止の流れ

一方で、M3やM4、Z4 M40iなどの他モデルでは、今後数年内にマニュアル仕様の生産が終了すると報じられています。
特にZ4 M40iに関しては、2026年のモデル末期にマニュアルが廃止される予定です。
また、次世代のM3(G84)では、マイルドハイブリッド化が計画されており、マニュアル対応が難しくなると予想されています。
ハイブリッド化がもたらす変化
BMWに限らず、ハイブリッドや電動化が進む中で、マニュアル車の存在意義は年々薄れています。
ハイブリッド車ではトランスミッション制御が複雑化し、最適な電動アシストを行うには自動変速機が不可欠となるため、マニュアルとの親和性が極めて低いのです。
これらの技術的事情が、マニュアル車消滅の流れを加速させていると言えるでしょう。
それでも残る“運転の楽しさ”とは何か
マニュアルが与える“操る喜び”
マニュアル車が愛されてきた理由のひとつは、ドライバーが車を自ら“操る”感覚を味わえる点にあります。
ギア選択、クラッチ操作、エンジンブレーキといった一連の動作が、機械との一体感を生み出します。
これは多くの自動車ファンにとって、単なる移動手段ではない“ドライビングプレジャー”そのものです。
テクノロジーが補完する楽しさ
しかし、BMWはこの「楽しさ」をEV時代にも継承しようと試みています。
たとえば、モーターの加減速に連動して擬似的なエンジン音を流す「IconicSounds Electric」や、ドライビングモードごとの感触の違いを際立たせるソフトウェア制御技術などがその一例です。
これにより、マニュアル操作がなくてもドライバーがクルマと“対話している感覚”を得られるよう工夫されています。
“人とクルマの関係”が再定義される時代へ
たしかにマニュアルトランスミッションは消えていく運命にあるかもしれません。
しかし、その精神――すなわち「人がクルマと一体になって走る」という理念は、BMWをはじめとした多くのメーカーが次世代の技術によって再構築しようとしています。
運転の楽しさは、形を変えて未来へと受け継がれていくのです。
まとめ:BMWが選んだ道とマニュアル派の選択肢
BMWのマニュアル車が直面している“馬力の壁”は、単なる出力制限ではなく、時代の転換を象徴する現象です。
高出力化、電動化、効率重視という潮流の中で、マニュアルは少しずつ舞台を降りようとしています。
しかし、3.0 CSLのような例外や、M2に残る可能性を見ると、まだ“完全消滅”ではありません。
マニュアル派にとっては厳しい時代ですが、「運転する楽しさ」を追い求める姿勢こそが、これからのドライバーズカーの進化を支えていく原動力になるでしょう。
Reference:bmwblog.com
よくある質問(FAQ)
Q1. BMWで現在マニュアルが選べるモデルはどれですか?
現在、日本国内で正規に購入可能なBMWマニュアル車は少なく、M2など一部のMモデルに限定されています。
Q2. 473馬力以上にマニュアルを搭載できないのはなぜですか?
6速マニュアルの耐久性が550Nmまでに制限されており、高出力エンジンには対応できないためです。
Q3. 今後のMモデルでもマニュアル車は登場しますか?
M2を除き、M3やM4などは今後マニュアル仕様が廃止される予定と報じられています。
Q4. 電気自動車にマニュアルトランスミッションは搭載できますか?
EVは構造上、トルク特性が異なるためマニュアルの必要がなく、BMWも非搭載方針です。
Q5. マニュアルの操作感をEVで再現する取り組みはありますか?
BMWは合成エンジンサウンドや触覚フィードバックなどで、運転の楽しさの再現を目指しています。
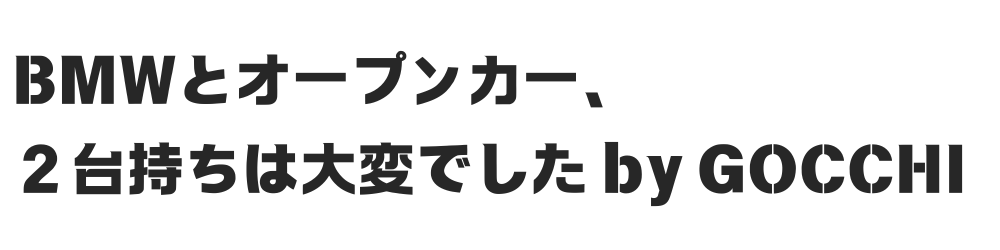

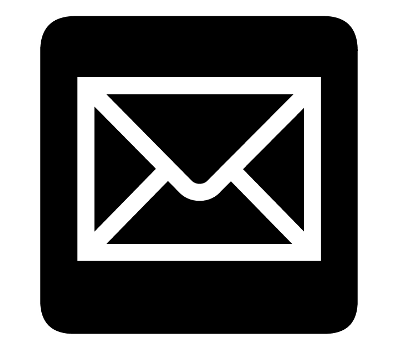


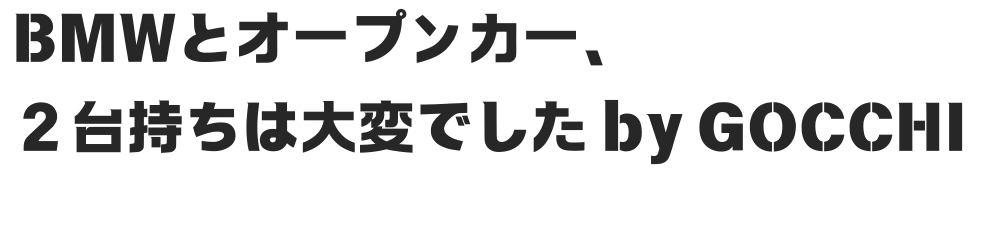
コメント