毎朝のトーストとコーヒーが日課という方、少なくないでしょう。私もその一人です。ですが最近、「パンを食べるな」という刺激的なタイトルの書籍や、グルテンフリー食事法の流行を目にするようになり、少し考えさせられています。
加えて、わが家の妻はパン教室に通っており、新作パンの試食が我が家のイベントに…ありがたい反面、グルテンフリーとどう向き合うべきか、複雑な心境です。
グルテンフリーとは?
グルテンフリーとは、小麦などに含まれる「グルテン」というタンパク質を避ける食事法のこと。テニスのノバク・ジョコビッチ選手が実践していたことで有名になりました。
「パンを食べるな」という本がベストセラーになった影響で、「糖質制限の一種?」と誤解されることもありますが、グルテンフリーの目的はあくまでグルテンによる体調不良の予防や改善です。
グルテンの体への影響とは
グルテンは小麦、大麦、ライ麦などに含まれるタンパク質です。このグルテンが腸に炎症を起こしたり、脳に影響を与えるといった研究結果が注目されています。
特に問題視されているのが「リーキーガット症候群(腸漏れ症候群)」。これは腸の粘膜に小さな穴が空き、異物が体内に入り込むことで、アレルギーや自己免疫疾患の原因となる可能性があるとされています。
ただし、すべての人にこの症状が出るわけではありません。グルテンに対して耐性がない人(非セリアックグルテン過敏症など)のみが影響を受けやすいとされており、その割合はアメリカでは約5%(20人に1人)とも言われています。
グルテンアレルギーは気づきにくい?
グルテンアレルギーの特徴のひとつが「遅発型アレルギー」であること。これは、花粉症のようにすぐに症状が出る即時型とは異なり、グルテンを摂取してから時間差で症状が現れるため、自分では気づきにくいのが特徴です。
体調不良の原因がグルテンだったと気づかず、ずっと不調が続く…というケースも少なくありません。そのため、「なんとなく疲れやすい」「原因不明の肌荒れが続く」といった人は、一度グルテンを控える生活を試してみるのも一つの手です。
でも小麦抜き生活は現実的?
ここで立ちはだかるのが「現実とのギャップ」です。私たちの食生活には以下のように小麦製品が深く関わっています:
- 朝食のパン
- ランチのラーメンやパスタ
- おやつのクッキーやケーキ
外食が多い人にとって、完全に小麦を排除するのは非常に困難です。グルテンアレルギーで明確な症状が出ていれば、強い動機になりますが、そうでなければ継続は難しいのが現実です。
できる範囲で「ゆるグルテンフリー」を
そこでおすすめなのが、完璧を目指さない「ゆるグルテンフリー」です。以下のような対策を無理なく取り入れてみましょう:
- パンを米粉パンやグルテンフリーのベーカリー製品に置き換える
- 麺類はフォー(米粉麺)やそば(十割)を選ぶ
- お菓子はナッツやフルーツにシフト
- 自炊を増やし、原材料に気をつける
また、家族の理解と協力も重要です。我が家では、パン好きな妻に協力してもらい、グルテンフリーの米粉パンに挑戦してもらうなど、小さな工夫から始めています。
まとめ:自分の体と向き合いながら取り入れる
グルテンフリー生活は一見ハードルが高そうに見えますが、「完璧」を目指さず、「できる範囲で意識する」ことで健康意識を高める良いきっかけになります。
朝食のパンを週に数回だけ米粉パンにしてみる、外食を和食中心にしてみる。それだけでも体が軽く感じるかもしれません。体調不良に心当たりがある人は、ぜひ一度、試してみてはいかがでしょうか?
そして最後に…パン教室帰りの妻が持ち帰る焼きたての香りは、なかなか抗えない誘惑です(笑)
『長生きしたけりゃパンは食べるな』の要約
本書『長生きしたけりゃパンは食べるな』(著:江部康二)は、日々の食生活に潜む小麦製品のリスクに警鐘を鳴らす健康指南書です。特にパンやパスタなどに含まれる「グルテン」や「糖質」が、血糖値の急上昇や慢性的な炎症、生活習慣病の原因となる可能性があると警告しています。
著者は、現代人の健康問題の多くが「糖質過多」によるものであり、主食を見直すことが健康長寿への第一歩だと主張します。ご飯やパンを控え、野菜やたんぱく質中心の食生活へシフトすることが、体重減少、糖尿病予防、認知症予防にもつながると解説しています。
本書は、糖質制限の医学的根拠と実践的な食生活の改善策を、図やデータとともに分かりやすく紹介しており、日々の食選びを見直したい方にとって有益な一冊です。
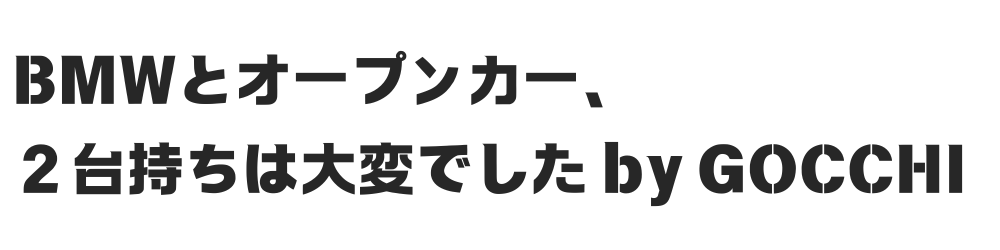
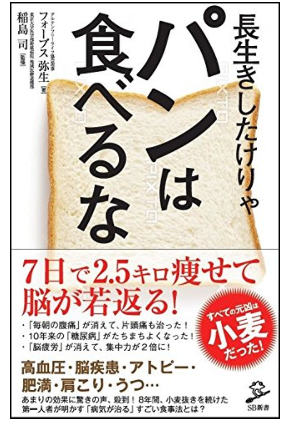

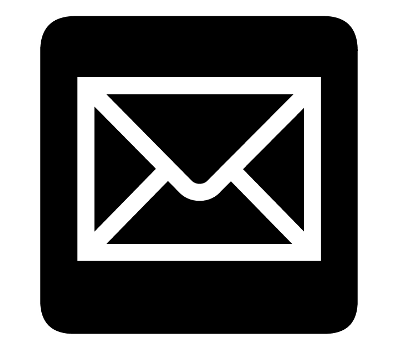


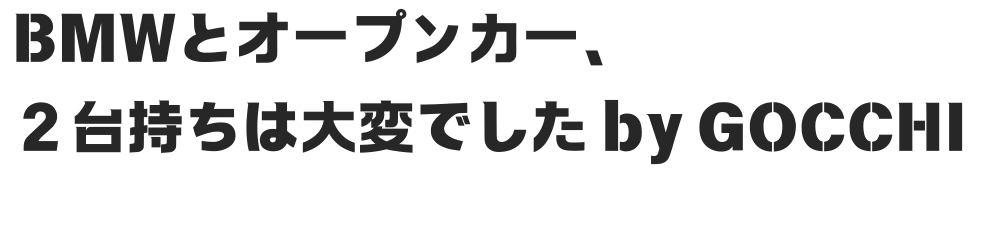
コメント