メルセデス・ベンツがBMWの2.0リッター直列4気筒ターボ「B48」エンジンの採用を検討しているという報道が注目を集めています。
長年のライバルである両社が動力源を共有する可能性は、業界でも極めて珍しい動きです。
本記事では、この提携話の背景と、BMW・メルセデスそれぞれにとってのメリットとデメリットを、できるだけ平易な言葉で整理します。
- 異例のエンジン提携:長年のライバルであるBMWとメルセデスが動力源を共有する可能性は極めて珍しい事例です。
- 提携の背景を解説:EV販売の失速、Euro7規制、政治リスクなど提携に至る要因を整理しています。
- 両社の利害を分析:BMWとメルセデスそれぞれのメリットとデメリットを明確にし、今後の展望を示しています。
歴史的ライバルが手を組む背景
EV販売の失速と戦略修正

メルセデスは電気自動車の拡販を進めてきましたが、2024年の米国市場ではEQシリーズ(EQEセダン/SUV、EQSセダン/SUVなど)の販売が想定を下回り、受注窓口の一時停止を含むテコ入れに動いたと報じられました。
EVに過度に資源を固定せず、当面はハイブリッドやプラグインハイブリッドも強化する方向に舵を切る現実的な判断が必要になっています。
Euro7とPHEV需要への即応
欧州で導入が見込まれるEuro7排出ガス規制に適合し、PHEV向けにも相性が良い量産エンジンを素早く確保できることは大きな利点です。
報道では、メルセデスが自社の新開発1.5リッター4気筒を持ちながらも、従来型PHEVやレンジエクステンダー用途には最適化されていない点が示されています。
既に多車種に展開されているBMWのB48を使えば、開発投資を抑えつつ規制と商品力の両立が図れます。
中国調達リスクの回避
メルセデスはコスト面から中国の吉利汽車(Geely)に4気筒の外部調達を求めた経緯があるとされますが、米国などの主要市場では中国製ユニット採用が政治的に難しくなっています。
欧州製のB48を活用すれば、そのリスクを低減しつつ、品質と供給の信頼性を確保できます。
想定タイムラインと生産体制
交渉は「かなり進んでいる段階」にあり、合意すれば2025年末までに発表の可能性があるとの見方があります。
一方で、実際のエンジン供給開始は2027年が目安とされ、オーストリア・シュタイア工場での生産や、関税回避をにらんだ米国内の共同工場検討といったシナリオも報じられています。
いずれにしても、ライバルから心臓部を調達するという点で、過去に例の少ない動きであることは確かです。
BMWのメリットとデメリット
メリット:生産ボリュームと収益の安定化
B48はBMWおよびMiniの幅広い車種で採用される量産エンジンです。
メルセデス向けの追加需要が生まれれば、シュタイア工場の稼働率はさらに高まり、長期的な収益源の安定化につながります。
欧州発の安定供給は、為替やサプライチェーンの変動に対する耐性も高めます。
メリット:技術ブランドの強化
BMWはこれまでもモーガン、イネオス、ランドローバー、トヨタなど外部へのパワートレーン供給実績を重ねてきました。
直接の競合であるメルセデスから選ばれることは、「信頼性」「効率」「適合性」における技術評価の裏づけとなり、エンジンサプライヤーとしてのブランド価値を押し上げます。
デメリット:差別化の希薄化と競合強化
ライバルに自社の強みとされる動力源を提供することで、商品面の差別化が薄れるおそれがあります。
車両全体の味つけは各社で異なるとはいえ、同一エンジンの採用は「走りの個性」の説明が難しくなる局面を生みかねません。
供給条件次第では、自ら競合の競争力を高める結果にもなります。
デメリット:供給制約と地政学リスク
共同の米国工場構想は関税やロジスティクスの面で理にかないますが、投資回収には安定した受注が欠かせません。
排ガス規制や燃費規制の変更、EVシフトの速度次第では、想定生産量が見直され、コスト負担が重くなる懸念も残ります。
メルセデスのメリットとデメリット
メリット:規制対応とコスト削減
BMWのB48エンジンを採用する最大の利点は、即座にEuro7排ガス規制に対応できる点です。
自社で新たに開発するよりも早く、市場に適合した車両を投入することが可能になります。
また既に量産実績のあるエンジンを外部から導入することで、自社の研究開発費を大幅に削減し、その分を電動化や次世代技術に振り分けることができます。
メリット:PHEVやレンジエクステンダーへの適性
B48はプラグインハイブリッドやレンジエクステンダー用途に適した設計がなされています。
メルセデスが自社で投入した1.5リッター4気筒は従来型PHEVとの親和性に欠けるとされ、即戦力として活用できるB48の存在は商品力の強化に直結します。
メリット:サプライチェーンと政治的安定
中国の吉利(Geely)からのエンジン調達はコスト面で有利とされたものの、米国や欧州市場では政治的リスクが高く、採用が困難でした。
その点、BMW製ユニットは欧州で生産され、米国での共同工場構想もあり、主要市場に安心して投入できます。
デメリット:ブランド独自性の喪失
最大の懸念は「メルセデスらしさ」の希薄化です。
長年自社開発のエンジンを誇ってきたブランドにとって、ライバル企業の心臓部を採用することは顧客からの見方を変えるリスクを伴います。
プレミアムブランドとしての独自性を失いかねない点は無視できません。
デメリット:ライバルへの依存と契約リスク
BMWからの供給に依存することで、契約条件や価格改定に左右されるリスクも生じます。
万が一供給が制約されれば、生産計画全体が揺らぐ可能性があります。
長期的なEV戦略とどう整合性をとるかも課題です。
なぜ今回の提携は異例なのか

BMWは協業に慣れている
BMWはこれまで、トヨタと共同開発したZ4とスープラをはじめ、ランドローバーやイネオスへのパワートレーン供給など、他社との提携に柔軟に対応してきました。
こうした協業は、開発コストの分担や生産量の確保という観点から自然な選択といえます。
メルセデスは自社主義を貫いてきた
一方のメルセデスは、AMG GTやSLS AMGなど象徴的なスポーツカーをはじめ、基本的に自社開発を重視してきました。
もちろんルノー=日産との小型車分野での協業やBYDとのEVブランド設立といった事例はありますが、直接のライバルからエンジンを調達するのは極めて異例です。
今回の提携が意味するもの
この「ライバルから心臓部を受け入れる」という判断は、メルセデスが置かれている環境の厳しさを物語ります。
ただし全体を悲観的に見る必要はなく、短期的には合理的な戦略転換といえます。
他社と積極的に手を組んできたBMWと比べると、今回の合意は業界にとって歴史的な一歩であることに間違いありません。
まとめ:BMWとメルセデスの異例提携
BMWのB48エンジンをメルセデスが搭載する可能性は、長年のライバル関係を考えると極めて異例な動きです。
背景にはEV販売の不振や厳しい排ガス規制、コスト圧力があり、両社にとって短期的には合理的な判断といえます。
ただし、メルセデスのブランド独自性や長期的な戦略への影響といった課題も残ります。
この提携は、自動車業界全体が変化の中で生き残りを模索する象徴的な事例となるでしょう。
Reference:caranddriver.com
よくある質問(FAQ)
Q1. BMWのB48エンジンとは何ですか?
BMWが広く使用する2.0リッター直列4気筒ターボエンジンで、燃費効率と信頼性の高さからBMWやMiniの多くの車種に採用されています。
Q2. メルセデスがBMWエンジンを使うのは本当ですか?
正式発表はされていませんが、複数の報道で2027年からの供給開始が検討されていると伝えられています。:contentReference[oaicite:0]{index=0}:contentReference[oaicite:1]{index=1}
Q3. 過去にライバル同士でエンジンを共有した例はありますか?
BMWはトヨタやランドローバーへの供給実績がありますが、メルセデスが直接ライバルからエンジンを調達するのは非常に珍しい事例です。
Q4. なぜメルセデスは自社エンジンではなくBMW製を検討しているのですか?
Euro7排ガス規制やPHEV需要への即応が急務であり、開発コストを抑える狙いがあります。また、中国製エンジン調達の政治的リスクを回避する意味もあります。
Q5. この提携は今後の自動車業界にどんな影響を与えますか?
プレミアムブランド同士の協業は業界の常識を揺るがす動きであり、今後は他社間でも協力関係が広がる可能性があります。
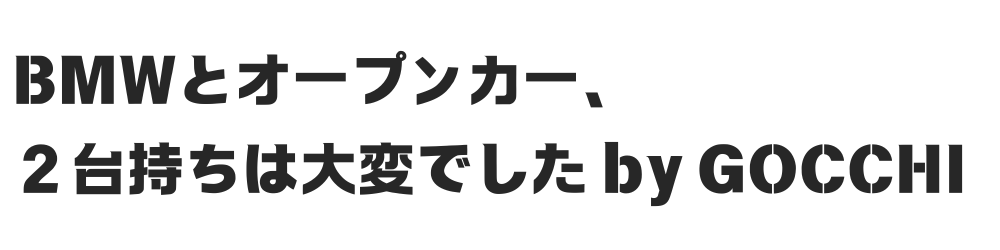



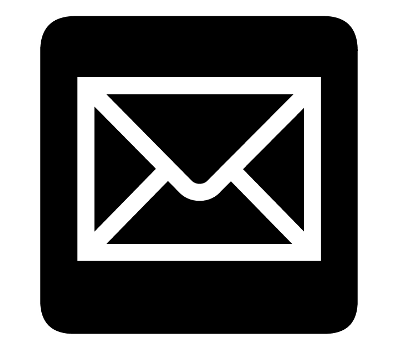


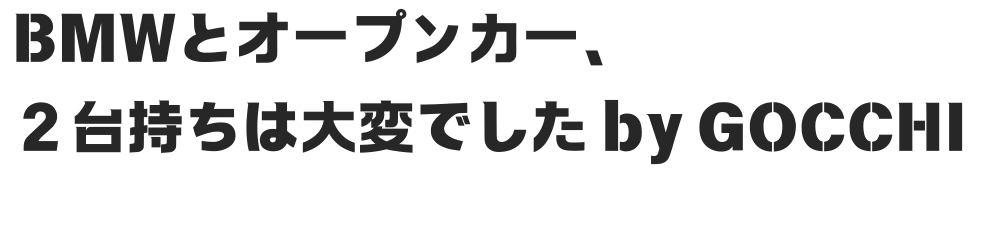
コメント