アルピナとBMW Mの間には、長年“紳士協定”が存在するという話があります。
Mはピュアスポーツを、アルピナはラグジュアリーで快適な超高速グランツーリスモを担い、互いに競合しないように住み分けてきたというものです。
本記事では、元アルピナCEOアンドレアス・ボベンシペン氏のインタビューをもとに、この紳士協定の内容と実際に存在したのかどうかを検証します。
さらに、BMW傘下に入った後のアルピナの実際の動きについても整理していきます。
- 紳士協定の要点:Mはスポーツ、アルピナは高速GTという役割分担の中身を簡潔に整理。
- 存在の有無を検証:明文化の有無と実務上の住み分け、後年の正式契約を区別して解説。
- 今後の体制と価値:BMW ALPINAの展望とBOVENSIEPENの役割、長距離“最速の移動”の意義。
結論と前提:Mは“最速のスポーツ”、アルピナは“最速の移動”
BMWとアルピナの紳士協定とは?
一般に噂される「紳士協定」は、両者が競合を避けるための暗黙の住み分けを指します。骨子は三点です。
第一に役割分担。BMW(とくにM部門)はピュアスポーツやサーキット最速を担い、アルピナは長距離を短時間で静かに走り切る“超高速グランツーリスモ”を担います。
第二に商品設計の方向性。アルピナは厚いトルク、再加速の速さ、100〜160km/h域での安定と静粛性を重視します。
第三に出力の線引き。最高出力(馬力)はMを上回らず、実用域で効く最大トルクは太く確保する——という整理が雑誌・ウェブ記事・フォーラムで長年語られてきました。
いずれも、ユーザーが求める“速さの質”が異なることを前提に、商品企画を重ねてきた結果として理解できます。
紳士協定は存在したのか?
協定の有無を断定する公式文書や明確な表現は、公表情報の範囲では確認できません。
一方で、インタビューでは
「より良いM3を作るつもりはなかった」
「長年フレンドリーな関係で協力してきた」
「父の代からラグジュアリー寄りになった」
「すべてを緻密に計画したわけではなく自然に分岐した」
といった趣旨が語られており、結果としての住み分けが実務上は機能していたと読み取れます。
つまり、文書化された協定の提示はないものの、両者の立ち位置が重ならない方向で成熟していった、というのが現実的な理解です。
現在のアルピナ活動と方針
BMWは「ALPINA」という商標・ブランド権を取得し、将来の“BMW ALPINA”商品はBMW側の枠組みで運用されます。
一方、従来の会社(旧アルピナ/現ボベンシペン)は、エンジニアリング供給やプロジェクト協力は継続します。
商品方針は大型ラグジュアリー領域(7系・X7相当など)での“長距離を速く・静かに・疲れずに”という価値を磨く方向に重心が置かれます。
また、既存オーナーへの部品・サービスについては近年モデルを中心に継続する姿勢が示されています。
要するに、これまで培った住み分けの実態は、ブランド権の契約という制度面と、開発・供給という実務面の双方で引き継がれているのです。
設計思想と走りの哲学 ― 紳士協定が生んだ二つの速さ
噂ではあるが紳士協定がBMWとアルピナの関係を形づくったとされるが、それは単に販売や出力の線引きを意味するものではありません。
それはクルマづくりの哲学そのものを分ける起点になりました。
Mが「最もスポーティなBMW」を目指して限界域の速さを磨く一方で、アルピナは「最も上質で速い移動」を追求するという明確な方向性を取ります。
この協定があったからこそ、両者は互いの領域を侵さずに独自の進化を遂げることができたのです。
協定が形にした“二つの速さ”
Mが重視するのはドライバーの操作と車体の一体感、つまり人とマシンが限界で調和する瞬間の速さです。
アルピナは逆に、移動そのものの質を高め、同乗者も快適に速く目的地へ着くことを目的としています。
サーキットでの最速タイムではなく、長距離を短時間で移動する「総合的な速さ」。
この考え方の違いが、まさに紳士協定の本質です。
走りのチューニング思想:緊張ではなく余裕を
Mのチューニングは、ドライバーが車の挙動を感じ取り、積極的に操作する楽しさを軸に設計されています。
エンジンは高回転まで鋭く伸び、ステアリングはわずかな入力にも即座に反応します。
一方でアルピナは、常用域のトルクと乗り心地のバランスを徹底的に磨き、余裕ある加速と上質な静粛性を優先します。
高速道路の継ぎ目やコーナー出口での安定感、長距離を走っても疲れないダンパーのセッティング――これらはすべて“最速の移動”を支えるための哲学です。
数値で見える哲学の違い
この思想の違いはスペックにもはっきり現れます。
たとえばM3コンペティション(G80)は最高出力510ps、最大トルク650Nm。
一方、アルピナB3は495psながらトルクは730Nmに達します。
最高出力ではMをわずかに下回りながら、実用域の力強さで上回る。
まさに「馬力では超えないが、トルクで勝負する」という紳士協定の暗黙のルールを象徴しています。
目的地に“速く、静かに、疲れずに”到着するための設計
アルピナの速さは、アクセルを大きく踏み込まなくても速く移動できる設計思想にあります。
トランスミッションの変速制御、遮音材の配置、足回りの柔軟性――すべてが“時間効率の良い移動”を実現するために最適化されています。
Mがドライバーの情熱を引き出すマシンだとすれば、アルピナは乗る人全員の時間を最短で豊かにするマシン。
紳士協定は単なる線引きではなく、この二つの速さの哲学を共存させるための無言のルールだったのです。
ブランド戦略とビジネスの住み分け
グループ内での競合を避ける合理的構造
BMWとアルピナの関係をビジネスの観点から見ると、紳士協定は単なる理念ではなく、極めて合理的な経営戦略でもありました。
M部門が「スポーツの象徴」としてブランド価値を高める一方で、アルピナは「成熟した富裕層のための上質な移動」を担うことで、顧客層のバッティングを避けていたのです。
両社が同じ土台を使いながら、異なる方向へ価値を拡張することで、BMWグループ全体の市場カバー率を広げる役割を果たしていました。
少量生産と高付加価値のビジネスモデル
アルピナは年間生産台数が約2000台前後と非常に限られています。
開発・製造・品質検査をブッフローの自社工場で行い、顧客仕様に応じたハンドビルド工程を維持してきました。
この少量高品質のモデルは、単なる「BMWの改良版」ではなく、完全に別の価値を提供する高付加価値ビジネスです。
Mがブランドイメージを牽引する量産スポーツであるのに対し、アルピナは利益率と顧客満足度を優先する職人ブランドとして共存してきたのです。
電動化時代に向けた再編とブランド権売却の意味

近年の欧州ではCO₂排出規制の厳格化により、小規模メーカーほど開発コストと罰金負担が増大しています。
特にアルピナのような少量生産ブランドは、独自認証を維持するだけでも大きなリスクを抱えるようになりました。
こうした背景から、アルピナは2022年に「ALPINA」商標とブランド権をBMWへ売却し、将来の生産・開発はグループ体制で進める決断を下しました。
これは吸収ではなく、長年の関係を制度化したものであり、ボベンシペン家は引き続きエンジニアリング部門を通じて協力を続けています。
ブランドの共存がもたらすシナジー
結果として、BMWグループはMとアルピナという二つの異なる価値軸を正式に内包する形になりました。
Mは走りの情熱を象徴し、アルピナは洗練と快適性の頂点を示す。
その住み分けは、競争ではなく補完の関係にあります。
電動化や自動運転の時代においても、この二つのブランドが異なる“速さの哲学”を体現することで、BMWグループ全体のブランドポートフォリオはより立体的になっていくのです。
今後の展望 ― “BMW ALPINA”の未来とBOVENSIEPENの新たな挑戦
BMW傘下で続く“超高速グランツーリスモ”路線

アルピナブランドは2025年以降、BMWグループ内の正式なブランドとして新たなフェーズに入ります。
今後は「BMW ALPINA」として、主に7シリーズやX7といった大型ラグジュアリーセグメントを中心に展開される予定です。
開発・生産・品質基準はBMW本体の枠組みに統合されますが、アルピナが培ってきた“長距離を速く・静かに・疲れずに移動する”という設計思想は引き継がれる見通しです。
つまり、電動化や自動運転の時代においても、アルピナらしいグランツーリスモの価値は失われないということです。
BOVENSIEPENブランドの独立と役割の変化

商標がBMWに譲渡されたあとも、ボベンシペン家が運営するBOVENSIEPEN GmbH(旧アルピナ)は存続し、エンジニアリングやプロトタイプ開発を中心とした事業を継続します。
これは従来の「車両メーカー」としての立場から、「開発パートナー」「コンサルティング・エンジニアリング企業」へと役割を変える動きです。
既存のアルピナオーナーに対するメンテナンスや部品供給も継続されることが明言されており、ブランドを支えてきた“人の技術”は今後も活かされ続けます。
電動化時代の課題とアルピナ流の進化
ボベンシペン氏はインタビューの中で、電動化による課題を率直に語っています。
バッテリーの重量増加や航続距離の制約により、これまでのような「軽く、速く、遠くまで走る」理想をそのまま実現するのは難しくなるとしています。
そのうえで彼は「技術が進化しても、快適かつ効率的な移動という価値は変わらない」と強調します。
今後のBMW ALPINAがどのように電動パワートレインを調和させ、これまでの哲学をEV時代にどう落とし込むのか――そこに次の焦点が置かれています。
まとめ ― 紳士協定が生んだ共存のかたち
BMWとアルピナの間に“紳士協定”が存在したのかという問いに対し、ボベンシペン氏は明言を避けました。
しかし、その発言の端々から、互いに競合を避けながら役割を分担してきた事実が浮かび上がります。
Mが「最もスポーティなBMW」を目指し、アルピナが「最も上質で速い移動」を追求する――この構図は半世紀以上にわたり、BMWグループのブランド戦略の中で機能してきました。
やがてその関係は正式な契約によって制度化され、現在のBMW ALPINAへと受け継がれています。
紳士協定とは、単なる暗黙のルールではなく、二つのブランドが互いを尊重し合いながら共に成長してきた歴史そのものを示す言葉なのです。
Reference:
 アルピナの未来:アンドレアス・ボベンシペン氏 | MotoMan Podcast 004
アルピナの未来:アンドレアス・ボベンシペン氏 | MotoMan Podcast 004
よくある質問(FAQ)
Q1. 「紳士協定」の中身は何ですか?
一般に語られる要点は、Mはピュアスポーツ、アルピナは超高速グランツーリスモを担当し、最高出力はMを超えず、実用域のトルクは厚く取る――という“住み分け”です。明文化の有無は公表されていません。
Q2. 紳士協定は本当に存在したのですか?
当事者からの明確なYes/Noは示されていません。ただし長年の発言やモデル特性から、実務上の住み分けが機能していたことは読み取れます。後年はブランド権の正式契約によって構図が制度化されました。
Q3. Mとアルピナは走りがどう違いますか?
Mは限界域での俊敏さとピーク性能を重視します。アルピナは100〜160km/h域の安定、再加速、静粛性など“移動の速さと快適さ”を重視します。同じBMWを土台にしつつ、味付けと目的が異なります。
Q4. いまの「BMW ALPINA」とBOVENSIEPENの関係は?
商標・ブランド権はBMWが保有し、新しいBMW ALPINAはグループ内で展開されます。一方、ボベンシペン側はエンジニアリング供給などで協力を継続し、技術とノウハウは生かされています。
Q5. 既存オーナーの部品・サポートはどうなりますか?
近年モデルを中心にアフターサポート継続の方針が示されています。詳細は各マーケットとモデル年式で異なるため、正規ネットワークでの確認が推奨されます。
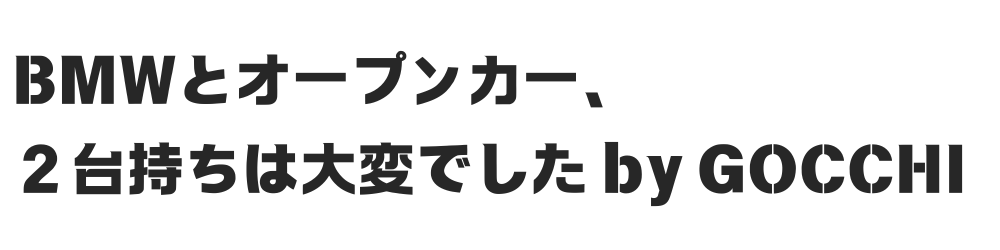

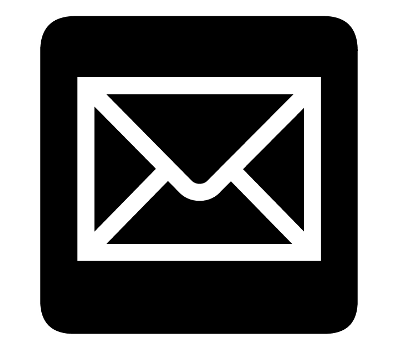


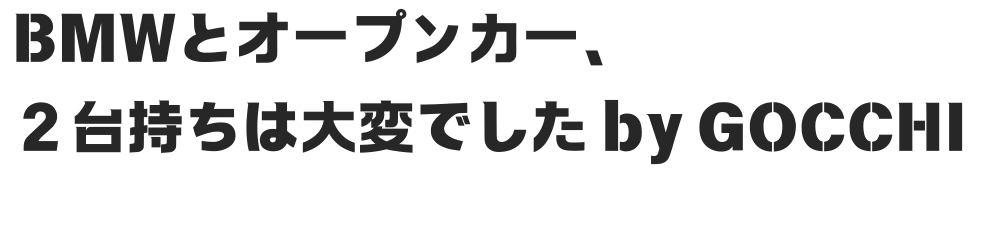
コメント